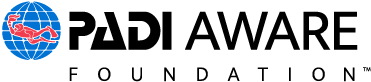2025年3月15日(土)、三重県・伊勢志摩にて、浜と海中のごみを一掃する合同清掃活動が実施されました。
舞台は、真珠のふるさと、三重県・志摩市の英虞湾(あごわん)。入り組んだリアス式海岸が広がるこの湾は、世界に誇る真珠養殖の聖地。日本三大真珠養殖地(三重県の伊勢志摩、愛媛県の宇和島、長崎県の対馬・壱岐)のひとつです。
海に浮かぶ黒いブイや、発泡スチロール製の白い「バール」と呼ばれる巨大な浮き。これらは、いかだに取り付けられ、アコヤ貝の養殖に欠かせない道具たち。しかし月日が流れ、役目を終えたそれらが、浜辺や海中に“産業廃棄物”として残されている現実も、見過ごせない問題として浮き彫りになってきました。



真珠の輝きの裏に、見えない課題あり
この現状に立ち上がったのが、三重県・志摩町の三重県真珠養殖漁業協同組合と、輸出真珠の品質向上を図り、消費者の信頼を確保し、真珠の輸出貿易の健全な発展を図ることを目的とした団体の日本真珠輸出組合。2024年から、地域ぐるみで浜の清掃活動に乗り出しました。
真珠は日本が世界に誇る輸出産業。その品質は折り紙付きですが、今、問われているのは“持続可能性”。日本真珠輸出組合は、真珠のライフサイクル全体を見渡し、サステナビリティの核心にある「養殖ごみ問題」に照準を合わせます。
しかも、生産現場は今、高齢化と後継者不足という二重苦にも直面。ごみの回収さえ、人手が足りない―そんな声が上がる中で、「一人は万人のために、万人は一人のために」の精神で、漁協・地域・企業が手を取り合いました。
2025年、活動の輪はさらに拡大。「陸上から見える海の近辺だけではなく、海の中もきれいにしよう」と、水中清掃の計画が本格始動。
水中ごみ拾い活動の Dive Against Debrisを推進しているAWARE(日本)に日本真珠輸出組合から声がかかったのでした。
真珠の養殖に携わる地元の業者や漁師の皆さまが海の恵みに支えられているように、私たちダイバーもまた、海があってこそ、その魅力を味わうことができます。「楽しい」だけで終わらせるのではなく、私たちダイバーはごみの回収・清掃などの環境保全活動を通じて、日々恩恵を受けているこの海に、感謝の気持ちを形にして届けたいと願っています。

海の底にも手を伸ばせ!水中清掃、始動!
地元である三重県・松阪のPADI 5スターIDセンター「シーポイント三重」の皆さんにも協力を依頼し、参画していただきました。現地調査から実施計画、参加者の集客に至るまで、万全の布陣で臨みました。

当日は、陸上班と水中班の二手に分かれて作業スタート。
陸上班は伝馬船(てんません)でごみの集積地へ。朽ちた木材や巨大な浮きの「バール」など、まるで動く廃材博物館のような漂着物を次々と回収します。
一方、水中班はビーチとボートの2グループに分かれ、ダイナミックに海底へ。ここ英虞湾の海底は、ふわふわとしたシルト(細粒堆積物)に覆われており、ひとたびフィンを動かせば、視界ゼロの濁流地獄。中性浮力のコントロールが試される、まさにダイバーとしての腕の見せどころでした。
水中班は、Dive Against Dbris の手順に沿って、水中から回収したごみの分別を実施しました。
水中から回収したごみは空き缶や包装類のほか、アコヤ貝の養殖網といった地域特有のごみも多数。陸と海で力を合わせ、大量のごみを回収することができました。












地元の味と未来への語らい
昼食には、地元漁師さんからご提供の志摩地方の郷土料理「てこね寿司」が振る舞われました。手でこねるように混ぜることから「手こね寿司」と呼ばれています。漬けた魚と酢飯を手でざっくり混ぜる、という漁師の豪快な調理スタイルがルーツ。その素朴で力強い味わいに、誰もが笑顔をほころばせました。



午後は、地域住民・漁業関係者・ダイバーが集まり、ワークショップを開催。「海ごみ問題の現在地」と「私たちにできること」をテーマに語らい、知見を深める時間となりました。
水中清掃を担当されたシーポイント三重のオーナーである増永氏より、水中の様子をご紹介。陸上の清掃をした方や地元漁師さんなどにとっては、水中の様子は興味深々。
締めくくりには、日本真珠輸出組合・専務理事の伊地知由美子氏が登壇。廃漁具を“資源”として再生する「水平リサイクル(Closed Loop Recycle)」の進捗報告が行なわれました。
英虞湾では、不要となった養殖カゴを同じく新たな漁具へと生まれ変わらせる、“世界初”の完全循環型モデルが誕生。これは単なる再利用ではなく、「循環型社会」のひな型として、全国に先駆ける取り組みといえます。



次なる一歩は、共に歩む未来へ
海の豊かさは、誰かひとりが守るものではありません。今回の活動は、地域、産業、そして個人が手を取り合った「協働の力」の証でした。日本真珠輸出組合とAWARE(日本)は、この流れを一過性で終わらせることなく、「継続は力なり」を信条に、今後も発展的な取り組みを目指しています。
一粒の真珠の裏には、たくさんの手と、たくさんの想いが込められているのです。